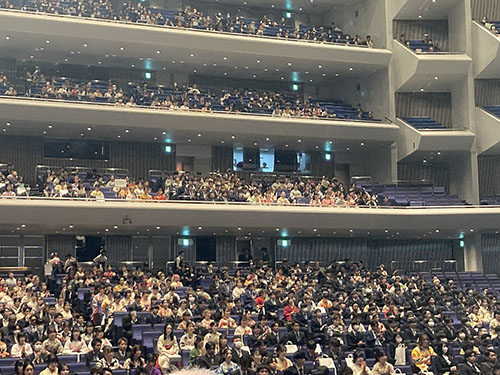松山市議会議員・若江進(わかえ すすむ)
第100代・松山市議会議長の経験を経て、
誰もが「住んで良かった」と思う松山市を目指し
2022年より5期目の松山市議会議員活動を行っています。
真の国際人とボランティアの育成
国際ボランティアとして、自分の技術を開発途上国の国造り人作りの為に役だてたいという思いから、青年海外協力隊に参加しました。現地でのボランティア活動を通じ日本の長所、短所も再発見できました。帰国後20年間、勤務のかたわら「青年海外協力隊OB会」や「協力隊を育てる会」の役員として活動してきましたが、これらの経験を生かし自分を育んでもらった松山市のために働きたいのです。国際化社会の現在、世界のなかの日本人として生きていくためにも若者たちを開発途上国で汗を流す体験を通じて、真の国際人を育てたいと思います。



スポーツを通した健全な青少年の育成
学生時代や協力隊員時代を通じてスポーツに取り組んできましたが、その中でスポーツが持つ教育的効果を痛感しました。協力隊員時代接した、途上国の子どもたちと若者の瞳の輝きを今も忘れることが出来ません。松山の青少年にも、そのような輝きをスポーツを通して取りもどして欲しいのです。そのためには、指導者の育成と充実が急務と考えています。



恵まれた自然と歴史を生かした町づくり
私が活動してきたインド洋にあるモルディブ共和国は、地球温暖化で水没の危機にあることを知りました。それに比べ、ふるさと松山がいかに恵まれているかを再認識しました。と同時にその恵まれた環境を生かしきれていない事実も痛感しました。 瀬戸内の穏やかな自然環境と、市内に温泉とお城を持ち合わせた全国でも数少ない恵まれた立地条件のもと、城下町が持つ歴史と文化を生かした町づくりを行います。誰もが「住んで良かった」と思う町、松山にしたいと思います。




松山市議会中継
令和6年(2024)第1回(3月)定例会は、次の日程で中継いたします。
| 月日 | 曜日 | 区分 | 摘要 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 02月16日 | 金曜日 | 本会議 | 開会、所信表明演説・提案説明 | 10 : 00 |
| 02月27日 | 火曜日 | 本会議 | 代表質問 | 10 : 00 |
| 02月28日 | 水曜日 | 本会議 | 代表質問 | 10 : 00 |
| 02月29日 | 木曜日 | 本会議 | 一般質問 | 10 : 00 |
| 03月01日 | 金曜日 | 本会議 | 一般質問 | 10 : 00 |
| 03月04日 | 月曜日 | 本会議 | 一般質問 | 10 : 00 |
| 03月05日 | 火曜日 | 本会議 | 一般質問、委員会付託 | 10 : 00 |
| 03月18日 | 月曜日 | 本会議 | 委員長報告、表決、閉会 | 10 : 00 |
- 審議状況により変更されることがあります。

松山市議会の日程や議案、議決結果をご覧いただけます。

松山市議会議員・若江進(わかえすすむ)のプロフィールやインタビュー記事をご覧いただけます。

松山市議会議員・若江進(わかえすすむ)の議員活動について、毎月の活動内容を年度別でご報告しています。
タグでたどる若江進の活動
2022 2023 えひめ・まつやま産業まつり えひめ万葉祭 ねんりんピック みらい松山 トライアスロン中島大会 ライオンズクラブ 三津厳島神社 三津浜 三津浜中学校 三津浜地区 三津浜小学校 三津浜花火大会 令和4年 令和5年 全国市議会議長会フォーラム 定例会 宮前グラウンドゴルフ 宮前スポーツ協会 平成船手組 建国記念の日奉祝 愛媛県 愛媛県青年海外協力隊 愛媛県青年海外協力隊を育てる会 拉致問題街頭啓発 松山まつり 松山卓球選手権 松山地区保護司会 松山城東ライオンズ 松山城東ライオンズクラブ 松山大学 松山市 松山市議会 松山市議会議員 松山市長杯卓球大会 松山短期大学 松山空港 松山維新の会 松山西高 椿神社 活動の軌跡 若江進 野志市長 青年海外協力隊

松山市議会議員
若江 進を育てる会
若江 進を応援していただける会員を募集しております。一口2,000円(何口でも可)個人会員に限る
振込先 銀行口座:愛媛銀行三津浜支店(普)3680232
振込先 銀行口座:伊予銀行本店営業部(普)4520001
郵便口座:01620-9-130064
宛名:若江 進を育てる会 代表 若江 進